テクノロジー株と株式市場の人工知能(AI)ブームについて、アライアンス・バーンスタイン(以下、「AB」)の株式ポートフォリオ・マネジャーが質問に答える。
AIの変革力をめぐる熱狂が引き続きテクノロジー株の追い風となっている。その一方で、投資家の多くが懸念しているのは、足元の株価やバリュエーションは過度に楽観的な利益予想を反映しているかもしれないということだ。AIをめぐる熱狂は今後も続くのか、ABの株式ポートフォリオ・マネジャーに考えと投資への影響について聞いてみた。
- 今日のAIブームはバブルなのか?
シュリ・シンヴィ(ストラテジック株式運用、最高投資責任者):AIそのもののバブルと株式市場のバブルの間には大きな違いがある。AIそのものは歴史的な変革をもたらす可能性が高く、それは私たちの人生において、最も大きな出来事の一つになるかもしれない。それでも、AIの活用事例や普及の度合い、さらにはその投資対効果(ROI)を野球の試合に例えるのであれば、現状はおそらくまだ1回か2回の途中であると言えるだろう。一方、AI開発企業やAIインフラ企業の株価という意味では、試合ははるかに先のイニングまで進んでいる可能性があり、それこそが株式投資家が考えるべき問題だ。ただし、こうした株式市場のいわゆるバブル状態は、AIの影響だけによるものではなく、金融政策や財政政策がもたらした過剰流動性が、AIよりもはるかに大きく影響していると考えられる。仮想通貨やミーム株(SNSなどで注目されているはやり株)を含む大半のリスク資産の価格が、AIとは何の関係もなく、上昇を続けているのはそのためだ。その上で、市場の過剰流動性がいずれ大幅に解消されるとすれば、それは早い方がよいのか遅い方がよいのか、株式投資家はリスクの高い選択を迫られていると言える。タイミングの判断は難しく、どちらを選んだとしても、判断を誤った場合のコストは大きい。
レイ・チウ(セマティック・イノベーション株式運用、最高投資責任者):AI革命全体をバブルと呼ぶのはおそらく単純すぎると考える。投資家は歴史的に、目先の変化を過大評価する一方、革命的な変化の長期的な影響については過小評価してしまうことが多かった。また、破壊的な変革は突然かつ劇的に起こる傾向があるにもかかわらず、投資家は通常、変化は徐々に直線的に進んでいくものだと考えている。こうした認識のずれは、投資家心理や株価の急激な変動につながる可能性があり、その結果、負債の大きな企業の株価にミスプライスが生じると、「バブル」がはじけるのである。

ITバブルがはじけたのは、ビジネスモデルを収益化できた企業が当時はほとんどなかったからである。ネットワーク関連企業が大きな負債を抱えて破綻した当時は、ストリーミングもソーシャルメディアも存在しなければ、モバイルアプリも普及していなかった。それでも、海底ケーブルや光ファイバーネットワークなどのインフラへの初期投資は不十分で、今日のような利用者数や通信量を支えるには、キャパシティがあまりにも不足していたと言える。今日のAIブームについて考える上で、投資家はこうした過去の教訓を忘れるべきではないと思う。
最後に、部品や電力の供給が大幅に不足すれば、便乗値上げなどの問題が起こり得ることも忘れてはならない。長期的に重要なのは、価格決定力を維持するとともに(以前の記事『関税の嵐の中、テクノロジー革命に投資する』ご参照)、新たな収益源を生み出すことができる企業を見極めることだ。AIに言及さえすればどのような企業でも株価が上昇する、いわゆる「上げ潮がすべての船を持ち上げる」状況は、いつか終わりを迎えると考えられる。簡単に言えば、足元の時価総額に値する真のAI勝者となる企業もあれば、そうではない企業も多いということである。そのため、現在の環境は、アクティブ運用に適しているとも言えるだろう。
ジョン・フォガティ(米国成長株式運用、共同最高投資責任者):AIストーリーが原動力となり、米国株式市場は2023年から2024年にかけて、特に巨大テクノロジー企業を中心に2022年の下落を取り戻す展開となった。AIテーマが株式市場の動向を支配する状況は2025年も続いており、エヌビディア以外にも、データセンター投資の拡大から恩恵を受けるAIインフラ企業が増えている。こうした話は単なる誇張ではなく、市場のテーマがいかに限られているか、国内総生産(GDP)に占めるAI関連設備投資の大きさからも垣間見ることができる。ただし、より重要な問題は、こうした傾向が今後も続くどうかである。
投資意欲の急激な拡大が今後も続くかどうかは、次の2つの重要な前提にかかっていると言える。つまり、1)AIの学習能力が引き続き拡大し、計算能力も強化されることで、汎用人工知能(AGI)が実現するという前提と、2)AI推論技術が十分な収益を生み、その収益が将来にわたって設備投資の拡大を支えていくという前提である。どちらかの前提が崩れ、設備投資が減速に転じるだけでも、「バブルの崩壊」を伴う株式市場の調整は起こり得る。そして、市場がAIストーリーに偏り、集中度の高いぜい弱な状態にある今日、株式市場の調整は負の資産効果をもたらすリスクもある。

ジム・ティアニー(米国成長株集中投資戦略、最高投資責任者):市場のぜい弱性については私もジョンと同じ考えだ。エヌビディアは先日、同社の大口顧客であるオープンAIに対して、最大1,000億米ドルの資金提供を行う意向を示した。オープンAIによるエヌビディアからの資金調達は、オープンAIがエヌビディアの最大顧客の一つであることから、その資金がエヌビディアの画像処理装置(GPU)の購入に使われるという取引の循環性とリスクを浮き彫りにしており、かつて破綻したペッツ・ドット・コム(ペット用品大手)や1990年代後半のITバブルを私は思い出す。ここでの問題は、オープンAIの巨額の支出に対して、同社のフリーキャッシュフローは何年もマイナスの状態が続いている点にある。そのため、熱狂的なAI設備投資も、市場が資金を引き揚げれば、急速に冷え込むリスクがある。AIの分野では、あらゆる予測がこの先何年も続く設備投資の拡大を前提としているものの、そうしたストーリーの実現を妨げ得る要因は多岐にわたる。例えば、より電力効率の高い半導体チップの登場、モデルの性能向上ペースの鈍化、電力供給の制約、AIによる生産性向上の限界、さらには過剰生産能力などがそうである。現状、AIの世界にもリスクはあるとABは考える。
トーステン・ヴィンケルマン(欧州/グローバル・グロース株式運用、最高投資責任者):私の考えでは、現状はいくつかの点において、ITバブルのような過去のバブルとは異なる。AIストーリーに関係のある米国、欧州、アジアの主な上場企業(エヌビディア、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ、サービスナウ、ASML、アプライド・マテリアルズ、TSMCなど)は現在、いずれも収益性が高く、株価のバリュエーションも説明可能な水準にあり、AI投資からプラスのリターンを上げている。
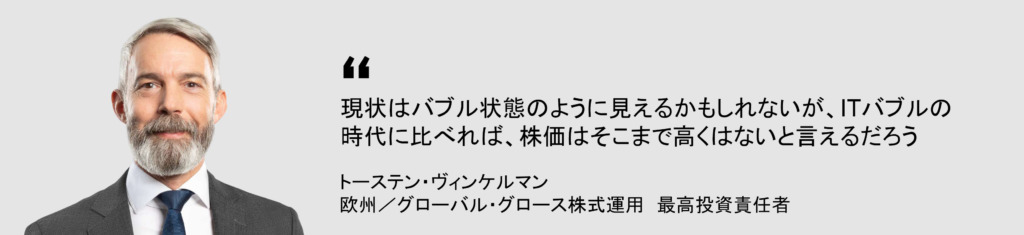
一方、バブルの要素がより強いのは、非上場の主要AI企業の一部(オープンAI、アンソロピック、シンキング・マシーンズ・ラボ、Z.aiなど)であり、そうした企業のバリュエーションは途方もなく高い水準にあるように私には思える。ジムも指摘したように、問題はこれらの企業が、ベンダーの資金に頼った循環投資とも呼べる手法を使って、AIインフラへの投資を増幅している点にある。また、こうした投資は上述の上場企業においても、受注や収益見通しの押し上げ要因となっている。
現状はバブル状態のように見えるかもしれないが、ITバブルの時代に比べれば、株価はそこまで高くはないと言えるだろう。
ケント・ハーギス(ストラテジック・コア株式運用、最高投資責任者):現状はまだバブルの初期段階にある可能性が高いと考える。市場ではAI銘柄の大幅な上昇が続いているが、そうしたなかにはクオリティの高い超大型銘柄もあれば、そうではない投機的な銘柄もある。また、非上場企業への巨額の資本流入も続いている(例えばオープンAIの時価総額は約5,000億米ドルであり、エックスAI(xAI)やアンソロピックの時価総額はそれぞれ1,500億~2,000億米ドル)。こうしたAIインフラへの投資ブームの初期段階を主に支えてきたのは、キャッシュフローが潤沢で、バランスシートも巨額の設備投資に耐えられる、ハイパースケーラーと呼ばれる企業(クラウドサービスを大規模に構築・運用する企業)であった。一方、その次の段階を見ると、借り入れによる事業の拡大や非上場企業の高いバリュエーション、さらには循環投資やリスクの高いプライベート・クレジット取引など、より不安定な資金源に支えられた投資が徐々に増えつつある。こうした動きは、資本の規律が弱まり、リターンを追い求める投資家が増えるなか、過度な投機に拍車をかけ、システム全体のリスクを高める要因となっている。AIは確かに革命的なテクノロジーではあるが、それに対する投資額はABの見通しによれば、これまでITバブルの時代にしか見られなかったような水準をも上回る可能性がある。重要な危険信号はこのほかにもいくつかあり、タイミングは分からないものの、市場の調整がいつか起こる可能性は高いと考えられる。
- AIの真の可能性と過大評価を、投資家はどうすれば区別することができるのか?
ジョン:AIは機械学習を通じて、コンピューター・プログラミングの進化やデジタル広告分析への移行という効果をもたらした。さらに、AIへの期待は、ROIの確実な向上につながる明らかなビジネスの成功だけにとどまらない。アクティブ運用会社であるABは、AIという新たな計算モデルが持つ力を信じており、AIの効果的な導入が生産性の向上や高い収益性の維持につながるような企業を発掘したいと考えている(以前の記事『AI vs. Demographics: The Strategic View』(英語)ご参照)。ただし、そうした企業の成功は一定のペースで進んでいくものではなく、AIの導入により時間がかかったり、段階的なモデルの改良が必要になったりすることもあるだろう。時間という制約のなか、市場ではAIの導入効果よりも、AIへの投資意欲を高く評価する状況が続いていると言える。

ジム:AIのさらなる可能性を見極める上では、2026年の設備投資の伸びや新たな収益モデルのほか、企業の経営陣が語る費用対効果の事例に目を向けることが、投資家には求められる。
レイ:2025年初めの「ディープシーク」による発表が、AI推論技術の導入における転換点となり、現在はAIによる出力のさらなる高速化が進んでいると言えるだろう。エヌビディアによるオープンAIへの投資は、簡単に言えば、極めて資金力の高い巨大テクノロジー企業にディスラプター(既存の秩序を破壊する革新的な企業)が対抗していくための資金提供であり、そうした巨大企業が支配する市場においては、高速コンピューティングの導入の加速が求められている。また、テクノロジー分野の超大型企業にとっては、AIに投資しない選択肢は全くなく、攻めと同じくらい守りにもAIが重要というABの見方は変わらない。
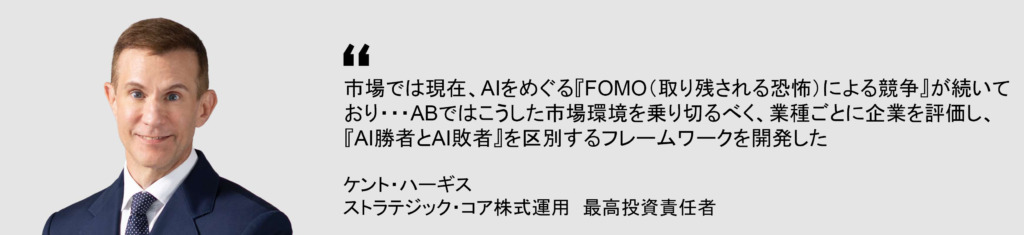
ケント:AI関連の設備投資の勢いを正当化するには、その根底にあるテクノロジーが進化を続ける必要がある。大規模言語モデル(LLM)は驚異的なペースで進化しており、それは主にLLMが学習と同時に計算能力を拡大してきたためである。また、より最近では、とりわけポストトレーニング(事後学習)技術や論理推論モデルにも大きな期待が寄せられている。長い目で見れば、AIの導入がさらに広がり、人間の仕事を実質的に代替することが、持続的なリターンの実現には必要であると言えるだろう。コードの作成や文章作成支援、さらにはコンテンツ作成や顧客サービスなどの分野では、AIが既に初期の成功を収めており、巨額の設備投資の将来的なROIを占う先行指標として、ABではこうした進化を注視していく方針である。仮に進化のペースが緩まるようなことがあれば、AIトレードの巻き戻しは避けられないと言えるだろう。
市場では現在、AIをめぐる「FOMO(取り残される恐怖)による競争」が続いており、過少投資のコストは過剰投資のコストを上回るという、マーク・ザッカーバーグ氏や著名なテクノロジー企業経営者の発言は、そうした状況をよく表していると言える。ABではこうした市場環境を乗り切るべく、業種ごとに企業を評価し、「AI勝者とAI敗者」を区別するフレームワークを開発した。サイクルのタイミングを計ることが本質的に難しいのはこれまでどおりだが、真のAI勝者の見極めを重視したボトムアップのアプローチには、大きな超過収益を生む力があるとABは考える。
シュリ:初期のAIプロジェクトの成否は確かにまちまちだったものの、AIが過大評価されていると考えるのは早すぎる。そうした失敗の背景には、初期のAIの能力不足だけでなく、AIの導入に向けた企業の準備不足もあったためだ。その一方で、AIを使ったコードの作成によって企業の業務効率が25~40%ほど改善するなど、初期段階から大きな成功を収めた分野もあり、顧客サービスの分野においても大きな成功例は見られる。また、医療の分野でも、AIの活用が請求処理にかかる時間やコストの大幅な削減につながっている(以前の記事『AIの進歩はヘルスケア株をよみがえらせる力になれるか?』ご参照)。今後さらに大規模な活用事例が生まれてくるのは間違いないものの、それがどのようなものになるかを事前に知ることはできない。例えば、iPhoneが初めて登場したのは2007年で、ウーバー(Uber)が開発されたのは2010年であり、さらに広く利用されるようになったのはその何年も後の話だ。つまり、AIについても、将来どのような活用が可能になるのか、私たちにはまだ想像すらできていないということである。
間違いなく言えるのは、今後はあらゆる企業や産業でAIが活用されるようになり、攻めではなくても守りとしてのAIの導入が必要になるということだ。導入の遅れを取り戻すには、極めて大きな技術的な負債と競争上の不利を克服しなければならず、そのような遅れを受け入れられる企業はない。最後に、AIがもたらす可能性は、ホワイトカラー業務の効率化をはるかに超えている。新たなAI技術の応用は、ロボットや例えば車の自動運転など、物理的な分野でも既に進められているためである。私たちが今後注目すべき最も重要なポイントは、1)モデルや応用技術の進化が続いていくか、2)トークンコスト(AIの利用コスト)の低下が続いていくか、そして3)AI導入企業全体の平均的なROIではなく、導入の先頭に立ち、成功を収めた企業のROI(ある企業が成功を収めた場合、他社はそれに追随せざるを得なくなるため)であると考えられる。

- 株式投資家にとって、リスクを取りすぎることなく、AIの可能性をリターンに変える方法はあるか?
ケント:バブルの状況下では、投機的でクオリティの低い企業が短期的にアウトパフォームすることも多い。一方、行き過ぎた投機がAIエコシステムの各所に広がり続けるなか、規律を維持し、企業のクオリティに焦点を当てる重要性が高まっている。長期的に最も有効なアプローチは、AIの活用が大きな利益をもたらすだけでなく、基幹ビジネスの堅調なファンダメンタルズがリスクの低減につながるような企業を見極めることであると考える(以前の記事『How to Capture AI Innovation in a Risk-Aware Equity Portfolio』(英語)ご参照)。いかなる投資にも常にリスクはあり、特にAIのような変化の早い成長テーマには注意が必要であるものの、ABの投資戦略はダウンサイド・リスクを最小化しつつ、魅力的なリスク調整後リターンを追求するものである。それはつまり、長期的に複利で価値を高めることができる、持続性とクオリティの高い企業に投資をするということであり、投機的なAIストーリーから一時的な利益を得ようとするものではない。
シュリ:AI関連銘柄への投資においては、複数の銘柄を機動的に組み合わせるアプローチが投資家には求められる。それは勝者と敗者を早い時期に見極めることはほぼ不可能だからである。ITバブルから学ぶべき教訓は、1999年の時点におけるIT勝者はアメリカ・オンライン(AOL)やヤフーであったかもしれないが、ブームの先駆者であった両社が最終的には後発企業に取って代わられてしまったという事実である。最終的に大きな勝利を収めたグーグル、メタ・プラットフォームズ、アップルなどの企業は、明らかな先駆者であったわけではない。AI関連銘柄への投資において、状況変化に対応できる機動性とアクティブ運用による銘柄の厳選が、極めて重要なのはそのためだ(以前の記事『マグニフィセント・セブン:もはや一枚岩ではない』ご参照)。AI関連企業を3つのグループ、すなわち直接的な受益者、間接的な受益者、そして利用者に分け、幅広くエクスポージャーを分散するのが賢明なアプローチであると考える。
AIは多くの産業に破壊的な変革をもたらすものであり、そうした分野における現在のリーダー企業は、「イノベーターのジレンマ」(優れた大企業がそれほど強くない新興企業に市場を奪われてしまうこと)に直面することになるだろう。そのため、一部のソフトウェア企業やITサービス企業、さらには人材派遣企業など、AIに取って代わられるリスクがある企業への投資を避けることも、投資家にとっては機動性や分散と同じくらい重要だ。
レイ:歴史的に見れば、バブルの「崩壊」は通常、債券市場から始まるものであり、資金繰りの困難を理由に企業が利払い不能に陥ることで生じるものである。今日のAI関連企業を見る限り、バブルが崩壊しつつあると判断するのは時期尚早と考える。しかしその一方で、プライベート・クレジット市場の動向には注意が必要だ。仮にバブルが発生した場合、それが最初に表れるのは、プライベート・クレジット市場であると考えられるためだ。
ジョン:今日のAIインフラ整備は、2000年前後のインターネット通信インフラの構築とは顕著に異なる。具体的には、今回は当時に比べて負債による資金調達が今のところ少ないほか、差し迫った需要を満たす必要があるという意味においても、ダークファイバー(未使用の光ファイバー)の構築が中心だった当時とは状況が異なるということである。それでも、ハイパースケーラーの売上高に対する設備投資支出の比率は倍増しており、その点はITバブルの時代と変わらない。将来的な支出の減少が緩やかなものであれ急激なものであれ、設備投資サイクルにはピークがあり、それは株価のバリュエーションも同じである。足元のインフラ構築フェーズがどのような終わりを迎えるか想像してみると、ITバブルの結末がそうであったように、今はまだ市場のリーダーではない企業が、AIを活用して利益を上げている可能性もあると考えられる。そのようなAI導入企業を発掘することが、インフラ開発の時間軸やROIに左右されない、超過収益の獲得につながると言えるだろう。
トーステン:すべて正しい指摘だ。その上で、ABの投資戦略は、AI関連企業のなかでも「金の採掘企業」ではなく「つるはしやシャベルを売る企業」、すなわちインフラを提供する企業を重視している。また、AIインフラ企業への投資において、ABが常に意識しているのは、将来の企業収益のなかでも「通常」事業による収益であり、明日にでも中止や延期となるリスクのある、AIブームによる収益がどれだけあるかではない。
当資料は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーのCONTEXTブログを日本語訳したものです。
オリジナルの英語版はこちら
本文中の見解はリサーチ、投資助言、売買推奨ではなく、必ずしもアライアンス・バーンスタイン(以下、「AB」)ポートフォリオ運用チームの見解とは限りません。本文中で言及した資産クラスに関する過去の実績や分析は将来の成果等を示唆・保証するものではありません。
当資料は、2025年10月22日現在の情報を基にアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが作成したものをアライアンス・バーンスタイン株式会社が翻訳した資料であり、いかなる場合も当資料に記載されている情報は、投資助言としてみなされません。当資料は信用できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に掲載されている予測、見通し、見解のいずれも実現される保証はありません。また当資料の記載内容、データ等は作成時点のものであり、今後予告なしに変更することがあります。当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。当資料中の個別の銘柄・企業については、あくまで説明のための例示であり、いかなる個別銘柄の売買等を推奨するものではありません。アライアンス・バーンスタイン及びABはアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。アライアンス・バーンスタイン株式会社は、ABの日本拠点です。
当資料についてのご意見、コメント、お問い合せ等はjpmarcom@editalliancebernsteinまでお寄せください。
「株式」カテゴリーの最新記事
「株式」カテゴリーでよく読まれている記事
アライアンス・バーンスタインの運用サービス
アライアンス・バーンスタイン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303号
https://www.alliancebernstein.co.jp/
- 加入協会
-
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
当資料についての重要情報
当資料は、投資判断のご参考となる情報提供を目的としており勧誘を目的としたものではありません。特定の投資信託の取得をご希望の場合には、販売会社において投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず詳細をご確認のうえ、投資に関する最終決定はご自身で判断なさるようお願いします。以下の内容は、投資信託をお申込みされる際に、投資家の皆様に、ご確認いただきたい事項としてお知らせするものです。
投資信託のリスクについて
アライアンス・バーンスタイン株式会社の設定・運用する投資信託は、株式・債券等の値動きのある金融商品等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。リスクの要因については、各投資信託が投資する金融商品等により異なりますので、お申込みにあたっては、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をご覧ください。
お客様にご負担いただく費用
投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります
- 申込時に直接ご負担いただく費用…申込手数料 上限3.3%(税抜3.0%)です。
- 換金時に直接ご負担いただく費用…信託財産留保金 上限0.5%です。
- 保有期間に間接的にご負担いただく費用…信託報酬 上限2.068%(税抜1.880%)です。
その他費用:上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アライアンス・バーンスタイン株式会社が運用する全ての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
ご注意
アライアンス・バーンスタイン株式会社の運用戦略や商品は、値動きのある金融商品等を投資対象として運用を行いますので、運用ポートフォリオの運用実績は、組入れられた金融商品等の値動きの変化による影響を受けます。また、金融商品取引業者等と取引を行うため、その業務または財産の状況の変化による影響も受けます。デリバティブ取引を行う場合は、これらの影響により保証金を超過する損失が発生する可能性があります。資産の価値の減少を含むリスクはお客様に帰属します。したがって、元金および利回りのいずれも保証されているものではありません。運用戦略や商品によって投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。また、ご投資に伴う運用報酬や保有期間中に間接的にご負担いただく費用、その他費用等及びその合計額も異なりますので、その金額をあらかじめ表示することができません。上記の個別の銘柄・企業については、あくまで説明のための例示であり、いかなる個別銘柄の売買等を推奨するものではありません。







